フライフィッシングを始めてみたいけど、どんな道具を揃えたらいいかよく分からないという声をよく聞きます。
特にロッドに関しては、かなり分かりづらいかなと思います。
フライロッドはバスロッドなど違いライト・ミディアム・ヘビーなどという分け方をされていませんし、ヤマメ用・バス用・シーバス用などと特に決まっているわけでもありません。
私なんかも同じロッドを、クロダイやシーバス、バス釣りやコイ釣りに使っていたりします。
そこで、フライフィッシングを始めてみたい方に向けて、どんな魚を釣るときにはどんなロッドを選べばいいか、少し解説していきたいと思います。
フライロッドの規格ってどんなの?
フライロッドの規格には、ざっくりと長さ・調子・硬さ(番手)の3つがあります。
まずはいちばん重要な硬さ(番手)について書いていきたいと思います。
というのも、番手によってある程度ロッドの長さは決まってしまいますし、調子もフライロッドに関して言えばほぼミディアムテーパーかスローテーパーで決まってしまうからです。
まあ、長さに関してはフローター向けのショートロッドやヨーロピアンニンフ用のロングロッドなど特殊なものはあるし、やたらとファーストテーパーなロッドもあったりはするのですが、そこは中級者以上になってからでもいいのかなと思います。
フライロッドの番手って何?
フライロッドは#1,#2,#3などロッドの強さ、硬さによって番号が振ってあり、番手と呼ばれています。
#1が一番柔らかく、#2,#3と数字が大きくなるごとに硬く強くなっていきます。
ざっくりとですが#1〜#3辺りまでが体長30cm以下の魚向け。
#4〜#6辺りがニジマスなどのやや大きめの魚向け、
#7以上になるとシーバスやシイラなどの大型の魚向けになる感じです。
ただ、この番手もぶっちゃけ規格があるわけでは無いようで、国産ロッドに比べて海外メーカーのほうが1番手ぐらい硬かったりします。
ロッドの長さについて
ロッドの長さは一般的に#1〜#3のロッドであれば7ft〜8ft。
#4〜#6のロッドでは7.5ft〜9ft。
#7以上のロッドになるとだいたい9ftになります。
ロッドの長さの決め方はいろいろあると思うのですが、渓流などの枝などが覆いかぶさっているようなところに行くときは7.5ftぐらいのロッド、それ以外は9ftのロッドでいいのかなと思います。
あとは、身長が高ければやや長めのロッドにしたりするなど、体格に合わせたりもします。
対象魚によってロッドの番手を分けてみた
主観ですが、対象の魚に対して、何番のロッドを使えばいいかチャートにしてみました。

あくまで私の主観なので、シイラを釣るのに#7のロッドを使ってはいけないのかと言われると、そんなことはないです。
ただ、釣り上げるまでに時間がかかってしまったり、大物がかかってしまうとロッドがへし折れる場合もありますが・・・
中には渓流でアマゴ、ヤマメを#5番ロッドで釣っている人もいるかと思います
一応の目安として参考にしていただければ幸いです。
まとめ
最近では、Amazonで中華製の安価なフライロッドも売っていて、フライフィッシングに対する敷居もだいぶ低くなったように感じます。
中華製の安いロッドというと安かろう悪かろうなイメージですが、評判を聞くかぎりそんなに悪くもないみたいです。
特にこのプレデターというロッドは、某YouTuberもかなりできが良いと言っていました。
日本のメーカーで言えばティムコが入門者用に、コストパフォーマンスの良いロッドを出しています。
もし興味があれば、まずは安いセットを買ってみて近くの川や海などでフライフィッシングをやってみてはいかがでしょうか。
おしまい。
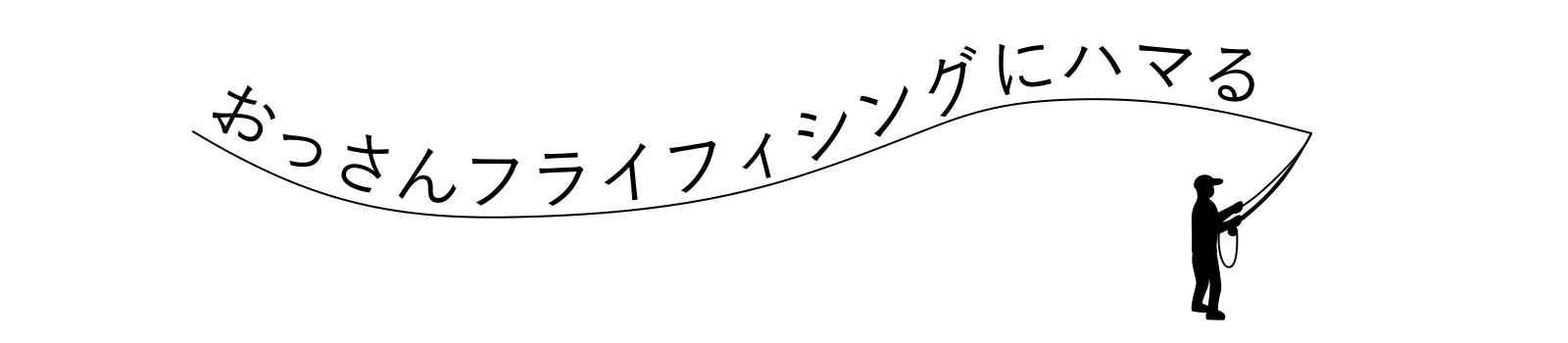












コメント